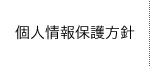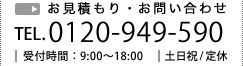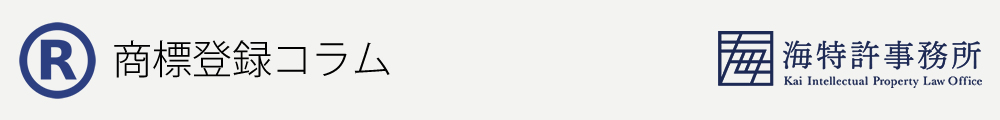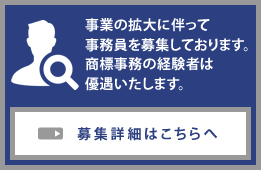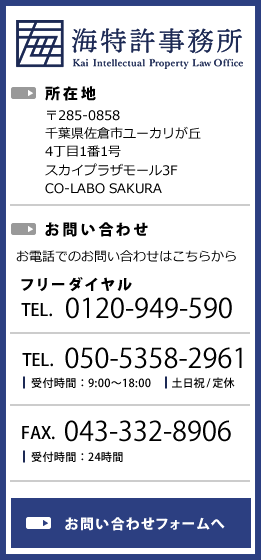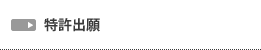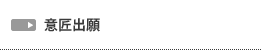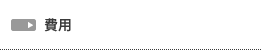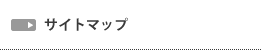日本の商標登録が歩んできた歴史|明治の商標条例から現代の商標法まで
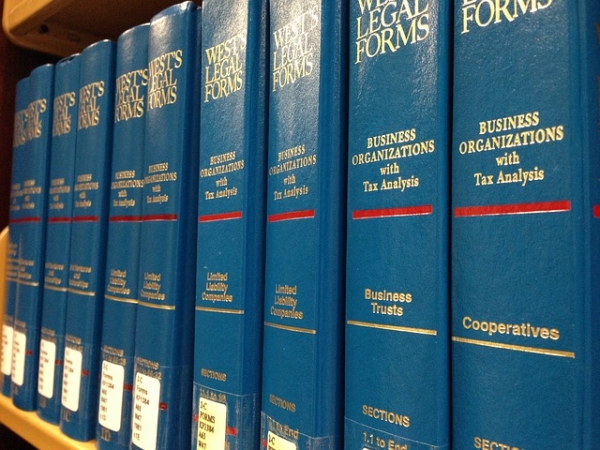
商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に、屋号や家紋が染め抜かれていて、それを商品の目印や広告代わりとしていたのが商標のはじまりとされています。
その後明治時代になって本格的に商標条例が制定され、やがて商標法と名称が変わり今日に至ります。これまで、商標登録はどのような歴史をたどってきたのでしょうか。
江戸時代から大正時代まで
明治時代に入って商標制度を作る動きがさかんになり、明治17年、高橋是清を責任者としてドイツ型の先願登録主義を採用した商標条例が成立しました。この時代の商標法は商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」の表記となっています。最初に登録された商標は京都府の平井祐喜による「膏薬丸薬」で、明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。
明治32年には商標条例は「商標法」へと変化を遂げ、明治42年改正では先願主義を原則としながらも、善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。また、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されることになります。
昭和から現代まで
平成に入り、平成3年改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。平成8年には商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されます。
平成11年にはマドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。平成17年には地域ブランドを保護するための「地域団体商標制度」が創設され、今日、多くの地域ブランドがこの制度を利用して商標登録をしています。
また、最近では平成26年に「新しい商標」として動き商標・ホログラム商標・位置商標などの概念も誕生し、著名な大企業を中心に登録出願が増加しています。
商標のはじまった江戸時代よりもっと古い時代では、奈良時代に建築された東大寺の瓦に銘が刻まれていたり、鎌倉時代に刀剣に刻印が刻まれていたこともあったとか。人々は昔から、目印になるようなものを何らかの方法で表示することで自分が作ったものをまわりにアピールしていたのですね。