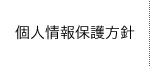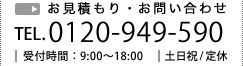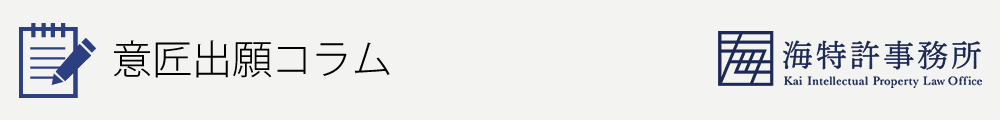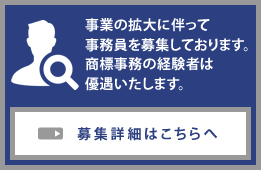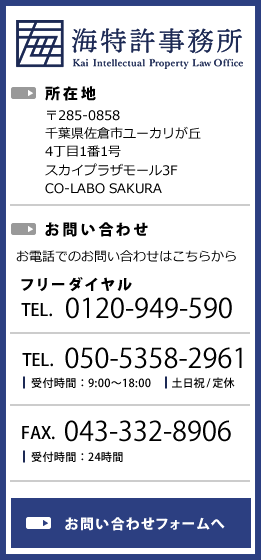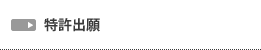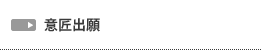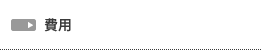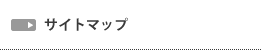登録意匠の保護期間は?取得した意匠権の権利維持期間を考えるチェックポイント

※法改正前(平成19年3月31日以前)に出願された意匠権の存続期間は登録日から最大15年です。
しかし、意匠権を維持するためには、毎年登録料が掛かります。
そのため、管理コストと意匠権を維持するメリットの費用対効果を見比べながら、取得した意匠権の権利維持を判断する必要があるのです。
今回は、この意匠権の権利維持期間を判断する上で指標となるチェックポイントについて解説いたします。
取得した意匠権の権利維持期間を考えるチェックポイント
しかし、販売を終了した後も、粗悪なコピー商品が出回り、オリジナル商品と混同して購入されることで企業のイメージが損なわれるリスクもあります。企業イメージと密接に繋がる製品デザインの意匠権を放棄する前には、ブランドやイメージを保護する観点も踏まえた慎重な判断が求められます。
また、販売期間中に製品デザインが広く市場に周知されブランド価値を持つようになったり、今後のビジネスにも繋がるような優れたデザインの意匠権であれば、できるだけ長期に意匠権を維持するという判断も考えられます。
さらに、意匠権は製品デザインの権利を貸与、あるいは譲渡するライセンスビジネスでの活用も考えられます。自社での製造や販売を止めた後も、他者へのライセンスの可能性を含め、今後のビジネス上の利用について広く検討する必要があるでしょう。
登録料は4年目、11年目に高くなります
意匠権の登録料は、20年間で2回年間の登録料が高くなります。
・初年度~3年目…年間8,500円
・4年目~10年目…年間16,900円
・11年目~20年目…年間33,800円
そのため、費用対効果と見合うか、将来的な売れ行きの見込みなどを含め意匠権の維持を重点的に見直すタイミングとしては。4年目・11年目が大きな節目となります。
意匠権を存続させる意匠登録料の支払いを忘れると、維持したい意匠権であっても、その権利が消滅してしまいます。
納付期限日までに納付できなかった場合、6ヶ月以内であれば登録料と同額の割増登録料をあわせて追納すれば権利を存続も可能です。
こうした納付忘れを未然に防止し、手続きを簡略化するため、平成21年から「特許料又は登録料の自動納付制度」も導入されています。
権利を維持する管理コストを削減するためには、ぜひ活用したい制度です。