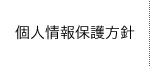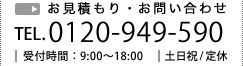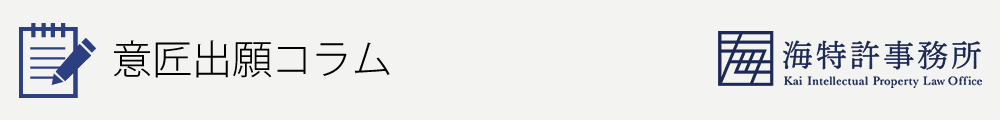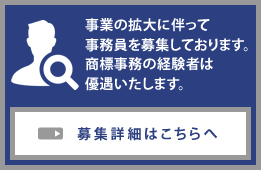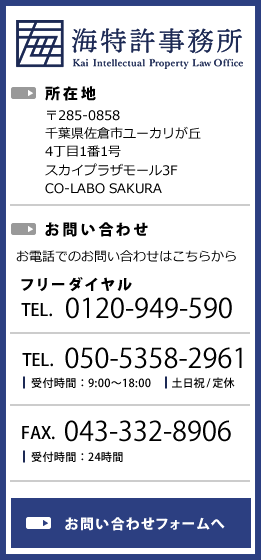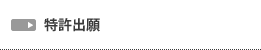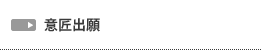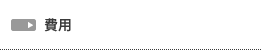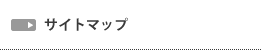海外展開を視野に入れた製品デザインを守る!国際的な意匠登録出願のポイント

それを防ぐためには、現地で意匠登録をする必要があります。
かつては自社製品の意匠について海外でも排他的独占権を得たければ、各国の官庁に意匠登録を出願しなければなりませんでした。
ところが、2014年に5月に国会の承認を得てハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入したことで、以前よりスムーズに海外で意匠権を登録できるようになっています。
なぜ国際意匠登録が必要なのか?
また、意匠制度そのものも日本と異なる国があり、海外で生産・販売をしていると他社が自社製品のデザインを意匠登録してしまい、突然権利侵害を訴えられるケースもあります。
そのようなことがないように、海外で生産拠点を作り、自社製品を製造・販売しようとするときには、意匠登録が必要不可欠と言えるでしょう。模倣被害の多い国については、模倣品が輸出されてどれくらいその国で売り上げるかということも考慮して出願するのが良いとされています。
特許庁の調べ(※)によると、模倣被害が多く発生しているのは2014年の時点では中国 64.1% 韓国18.9% 台湾18.0%とアジアが高い割合になっています。
※特許庁「2015年度模倣被害調査報告書」より
ハーグ協定のジュネーブ改正協定を利用するメリットとは
ハーグ協定とは、複数国における意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約のことで、現在50の国・政府間機関が加盟しています。こちらの協定を利用した意匠登録出願には、以下のようなメリットがあります。
・出願書類は英語・フランス語・スペイン語のいずれかで作成した書類を準備すればよい
・複数の意匠を一括して出願できる(1出願につき最大100意匠まで)
・国際登録はWIPO(世界知的財産所有権機関)で一元管理しているため、登録の更新や各種変更申請などはWIPOへの手続きだけですむ
・国際登録にかかる翻訳はWIPOが行うため書類の翻訳は必要ない 代理人も不要
・登録の可否がわかる時期が明確
国が違えば商習慣や制度も異なります。海外進出を検討している企業では、意匠権をはじめあらゆる知的財産権に関してしっかりと対策を講じた上でビジネスを展開しなければならないでしょう。
海外進出の際にどのように対策をすればよいか、またトラブルがあったときにどのように対処すればよいかわからないときは、知的財産権の専門家である弁理士に相談することをおすすめします。